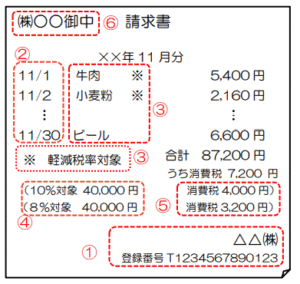インボイス制度やらないとどうなる!【事業者向け】簡単にわかりやすく解説<FP監修>
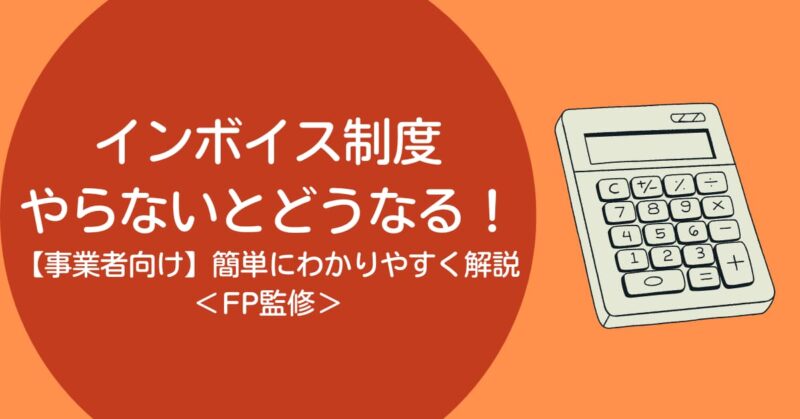
2023年10月1日から導入が開始される「インボイス制度」。
法人や個人事業主など事業者の経理業務に大きく関わるこの法改正。どのような内容なのかよくわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、事業者に向けて、インボイス制度とは何か、何が変わるのかといった点や必要な準備・注意点などを、FP監修のもとお伝えしていきます。
インボイス制度の要点を押さえて、しっかりと対応できるようにしましょう。
| 監修者:福田由美(ふくだ ゆみ)
米国MBA(経営学修士)、AFP(日本FP協会)、公的保険アドバイザー |
インボイス制度とは

「インボイス制度」とはどんな制度なのでしょうか。
インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日より導入される、消費税に関する仕入税額控除の方式のことを指します。
「インボイス制度」というのは通称で、正式には「適格請求書等保存方式」という名称の制度です。
簡単にいうと、この制度の導入後は、一定要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することで、仕入税額の控除が受けられるようになります。
国税庁のインボイス制度の概要にはこのようにあります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
インボイス制度の目的は、取引における消費税額を正確に把握することです。インボイス制度導入前は軽減税率8%と10%税率が混在していて複雑でしたが、インボイス制度導入後は正確に把握できるようになります。
消費税に関する不正やミスも防止できるようになります。
すなわち、インボイス制度を通して、消費税の透明性をアップさせ、正しく税金を納められるようにしましょう、というのが目的になります。
適格請求書とは
上記にも記載したように、インボイスとは「適格請求書」のことを指します。
「適格」とついていることからもわかるように、インボイスは、法律で定められた一定の要件を満たした内容でなければなりません。
今までの請求書では必須ではなかった項目の記載が必要になるため、請求書を出す側も受け取る側も、今回の変更に注意して対応する必要があります。
また、このインボイス(適格請求書)を発行できる業者は、「適格請求書発行業者」に限られます。
「適格請求書発行業者」になるためには、登録申請書を税務署長に提出して登録することが必要となります。
なお、インボイスに必要な内容や適格請求書発行業者の申請方法については、この記事の後半でご説明をしていますので、ぜひ読み進めてみてください。
仕入税額控除とは
続いて、仕入税額控除とは何でしょう。
消費税における仕入税額控除とは、生産や流通などの各取引の支払い時に発生する消費税が、二重課税にならないよう、その解消を図る制度です。
どうするかというと、売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引いた分を納税する、という方法をとります。
全ての支払取引が対象になるわけではなく、例えば給与など、非課税のものや消費税の対象外に当たるものを除いた、課税仕入に適用されます。
インボイス制度導入で何が変わる?
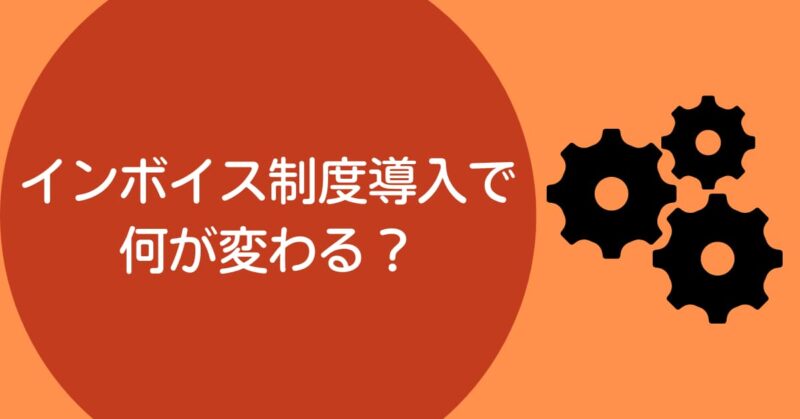
それでは、インボイス制度を導入することで、何が変わるのでしょうか?
ここでは、大きく変化する下記の3つの点について解説をしていきます。
- 適格請求書の発行が必要になる
- 消費税仕入税額控除を受けられなくなる
- 不正時のペナルティが強化される
適格請求書の発行が必要になる
インボイス制度のスタート後は、買い手である取引先から請求書発行を求められた際、売り手である登録業者は、要件を満たした適格請求書を発行する必要があります。
適格請求書では、これまでの請求書に記載してきた内容に、いくつかの項目を追加する必要が出てきますので、請求書のフォーマットも変更しなければならないケースもあります。
また、発行後は適格請求書の写しを双方にて保存しておく必要があります。
消費税仕入税額控除を受けられなくなる
インボイス制度の導入により、場合によっては、消費税仕入税額控除を受けられないケースも出てきます。
この制度では、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
例えば、課税事業者が免税事業者などの適格請求書発行事業者登録をしていない業者と取引をした場合、適格請求書を受け取ることができません。
そのため、その取引については、仕入税額控除が適用されません。
免税事業者が取引先に多い課税事業者にとっては、大きな影響が出てくるでしょう。
※ただし、経過措置として、一定要件のもと、免税事業者との取引においても、一定の割合を仕入税額として控除できる期間が設けられています。
免税事業者は、免税事業者のままではインボイスを発行することができず、インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を申請する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税事業者の認定を受けなくてはなりません。
また、免税業者の顧客が消費者であったり免税業者であったりする場合、または簡易課税制度を適用している事業者である場合は、免税事業者のままでも相手側の取引に影響は生じません。
不正時のペナルティが強化される
インボイス制度に違反した場合、罰則が科されるケースもあります。
例えば、登録をしていないのに勝手に登録番号を付けて請求書を交付した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が、罰則として科される可能性があります。
当たり前のことですが、今回の制度変更に、正しく対応をする必要がありますね。
消費税法では、以下のような規定が設けられています。
- 適格請求書類似書類等の交付の禁止規定(消費税法第57条の5)
- 上記禁止規定の罰則(消費税法第57条の5)に違反した者に対する罰則規定(消費税法第65条第4号)
参考:国税庁「インボイス制度導入後の是正に関する一考察-適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定を踏まえて-」
インボイス制度やらないとどうなる?
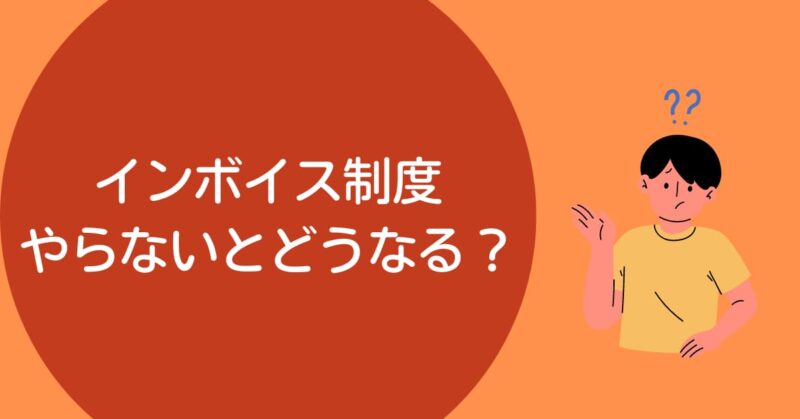
インボイスの発行事業者になるかどうかは、あくまで任意で、強制的なものではありません。
それでは、インボイス制度をやらないという選択肢をとった場合には、どうなるのでしょうか?
ここでは、適格請求書発行事業者として登録しない際のメリット・デメリットを解説していきます。
インボイス発行事業者になるか否かの判断材料にしてみてください。
免税事業者が登録しないメリット・デメリット
免税事業者は、消費税の納税が免除されている事業者です。
免税事業者にとって、適格請求書発行事業者に登録しないメリットとしては、消費税の申告や納付が不要なままになるため、手間がカットできるという点にあります。
一方、適格請求書発行事業者へ登録した場合には、今まで免税されていた消費税を納める義務が発生します。
デメリットとしては、適格請求書発行事業者の取引先から、適格請求書の発行を求められても発行できないことを理由に取引の継続を渋られたり、新しい取引を始められなかったりする可能性があります。収入の減少につながるケースも想定されます。
インボイスがないと販売先は仕入税額控除ができないので、あらかじめ消費税分を減らした額での発注をしたり、取引自体をやめようとしたりするかもしれません。
適格請求書事業者として登録するか否かは経営者の判断によります。
現状の取引先の状況なども鑑み、損益への影響を試算しながら、検討をする必要があるでしょう。
インボイス制度に登録しなくても影響を受けにくい人
インボイス制度に登録するかどうかは任意ですが、インボイス制度に登録しなくても影響を受けにくい人の条件としては、下記のようなケースが挙げられます。
| 対象者 | 概要 |
| 顧客が全て消費者 | 適格請求書発行業者になる必要は必ずしもない。消費者は直接消費税を納めることなく、仕入税額控除が不要なため |
| 顧客が免税事業者か簡易課税事業者のみ | 適格請求書発行業者になる必要は必ずしもない。適格請求書の発行が求められないため |
インボイス制度に必要な準備とは

2023年10月から導入されるインボイス制度ですが、事業者は下記のような準備をする必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 請求書のフォーマット変更
- 請求書発行システムの導入
- 社員教育
それぞれどのような内容かを見ていきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請
準備の第一段階として、インボイスを発行するために、適格請求書発行事業者として登録申請をする必要があります。
この手続きはe-Tax上で行うことができ、登録が完了すると、登録者番号が記載された登録通知書を受領できます。
請求書のフォーマット変更
適格請求書、すなわちインボイスの必要項目に合わせて、請求書のフォーマットを変更する必要があります。
従来の請求書に加える項目としては、主に下記の3点になります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
ちなみに、小売業や飲食店など、不特定多数の人を相手に販売活動をする事業者については、「簡易インボイス」というものも認められています。
簡易インボイスでは、通常のインボイスで必要な、受け取った人の指名・名称の記載は不要です。
また、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税等」は、いずれか一方の記載で問題ないと、されています。
加えて、インボイスは1つの書類のみで全記載項目を満たす必要はありません。
例えば同じ取引についての請求書と納品書、といった複数の書類を組み合わせて1つのインボイスとして取り扱うことが可能です。
参考:東京商工会議所「インボイス制度が導入!中小企業・小規模事業者が知っておくべきこと、準備しておくべきこと」
請求書発行システムの導入
インボイス制度では、商品・サービスを提供するのと同時に、請求書を発行する必要があります。
そのため、事業者はインボイスの項目に対応した適切な請求書発行システムを導入し、取引ごとに正確な請求書を作成できるようにする必要があります。
手書きやExcelを使用したインボイスも法律上は認められていますが、ミスの防止や管理の徹底のためにも、システムの導入はほぼ必須と考えた方がよいでしょう。
社員教育
インボイス制度開始後はこれまでの請求書発行・受け取り時とは異なるルールが適用されます。そのため、請求書を受け取って経理に回す担当社員の協力もかかせません。会社全体で対応できるよう、インボイス制度に関して理解を深めることが重要です。
その運用方法や重要性についての教育や、実践できるトレーニングの機会を設け、社内メンバーのインボイス制度への理解を十分にサポートしましょう。
インボイス発行事業者の義務と注意点

ここでは、インボイス(適格請求書)発行事業者が果たすべき義務と、注意点について解説していきます。
インボイス発行事業者の義務
インボイス発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合を除き、課税事業者である取引の相手方の要求に応じて、
- インボイスを交付する義務
- インボイスの写しを保存する義務
が課せられます。
なお、インボイスの交付義務が免除されるのは、下記の場合になります。
①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
⑤郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
返品や値引きを行った場合には返還インボイス、修正の際は修正インボイスの交付も適格請求書発行事業者の義務となっています。
インボイス発行の注意点
インボイスを発行できない事業者やフリーランスなど個人事業主への対応については、注意が必要になります。
例えば、課税事業者に転換しない場合に、消費税の全額を差し引いた額を取引額とするなどの通告等は、独占禁止法や下請法に抵触し、問題になる可能性があります。
一方で、免税事業者やインボイス非登録事業者と取引する場合には、仕入税額控除を受けられないことで、損益への影響が出てくることもあります。
免税事業者との取引が多い場合には、利益が減ることを見越して、売上計画を見直したり、固定費を見直したりといった対策を打つ必要が出てくるでしょう。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
HELP YOUがオンラインで経理業務をサポート

インボイス制度開始後の経理業務に不安のある方や、リソース不足で事業者としての変更対応が難しいといった方には、アウトソーシングの活用をおすすめします。
アウトソーシングとは、社内の一部業務を外部に委託することを指します。
オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」では、経理業務のサポートも承っています。
インボイス制度に関してもしっかり理解した経理のプロが担当するため、今回のような法改正等に対応したサポートも可能です。
HELP YOU とは
HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。
【HELP YOUのプラン】
<チームプラン>
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。
2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能
3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」
4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能
チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、経理業務はもちろん、他にも幅広い業務の依頼が可能です。
- 総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
- 経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など
- 人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
- 営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
- マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
- ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。
チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。
「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください!
HELP YOUの「経理プレミアム」
経理業務について、こんなお悩みはありませんか?
●今の経理担当者が退職したら他に対応できる人がいない
●インボイス制度などの法改正にちゃんと対応できているか不安…
●経理の数値を経営判断に活かせていない
そんな方におすすめなのが、HELP YOUの「経理プレミアム」サービスです。
経理プレミアムでは、経理業務の課題をまるっとお任せいただくことで、経理のプロがお客様の「こうしたい」を実現します。
- 経理コンサルサポート
経理コンサルタントがヒアリングを基に初期構築を行い、継続的に運用できる業務体制の改善・定着化を支援 - 経理業務の実務代行
経理コンサルサポートで構築した運用体制に基づき、実務アシスタントが専任で対応
【Basicプラン】
- 日常経理業務の実務代行
既存の経理業務オペレーションに基づき、実務アシスタントが専任で対応
※別途オプションで経理コンサルサポートも利用可能
ご質問や資料請求はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください!
インボイス制度を簡単に解説Q&A
ここまで、インボイス制度の概要をご説明してきましたが、理解が進みましたでしょうか?
こちらの章では、インボイス制度についてよくある疑問を解消すべく、Q&A形式で問いにお答えしていきます。
Q1:適格請求書発行事業者の申請方法を教えてください。
適格請求書発行事業者の登録申請手続きは、e-Taxで行うことができます。
e-Taxでの詳しい申請方法は、「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要」に記載されています。
e-Taxでの申請後、税務署における審査が通った際には登録者番号とともに「登録通知書」が送付され、適格請求書発行業者として認定されます。
Q2:適格請求書にはどんなことが記載されるのですか?
適格請求書には以下の6項目が記載されます。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①の登録番号と④⑤の項目が従来のものから追加になった点になります。
Q3:帳簿の保存だけで仕入れ税額控除が受けられるケースもあると聞きましたが本当ですか?
請求書等の交付を受けることが困難な取引の場合に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が認められます。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
Q4:フリーランサーの場合も「適格請求書発行事業者」の申請手続きをする必要がありますか?
消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず適格請求書発行事業者となることは、その事業者の任意とされています。個人事業主などフリーランスの場合も同様です。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録制度」
Q5:請求書や領収書はすべて必要ですか?
一部、請求書や領収書の交付を免除されているケースがあります。これは電子化されてない紙の請求書や領収書でも同様です。
例えば、公共交通機関の運賃や郵便切手を対価とする郵便サービスなど、適格請求書を交付することが困難な場合です。
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」
Q6:2022年度分の申告から紙の領収書は認められないのですか?
こちらは電子帳簿保存法との絡みとなりますが、電子取引に係る電磁的記録保存への移行のための宥恕(ゆうじょ)措置があります。
2022年1月1日~2023年12月31日の間に行った電子取引については「やむを得ない事情があると税務署長が認め、かつ、書面に出力して提示等の求めに応じることができるようにしている」のであれば、紙の領収書も認められます。
参考:財務省「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」
インボイス制度のまとめ
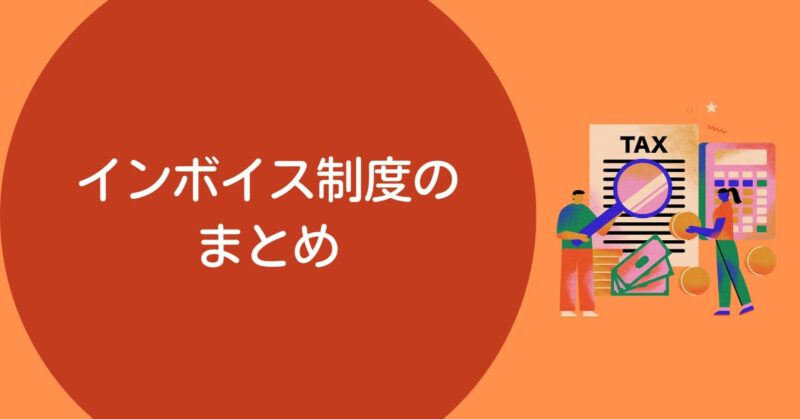
日本の消費税制度において、大きな転換点とも言えるインボイス制度の導入。
インボイス制度の内容や準備すべきこと等を事前に押さえておくことで、しっかり対応できるようにしておきましょう。
インボイス制度への対応など、経理業務でのお困りごとは、「HELP YOU」など、アウトソーシングサービスを導入することも一つの手段です。
これを機に外注という手段も検討してはいかがでしょうか?
この記事が、インボイス制度の更なる理解や制度への対応に役立ちましたら幸いです。
【関連記事】
経理業務はHELP YOUにおまかせ
膨大な時間がかかる上に、知識を必要とする経理業務。
毎月・毎年発生する作業に追われて、大事な業務に手が回らなくなっていませんか?
「大量の仕訳作業が大変」
「本当はもっと別のことに時間を使いたいのに…」
「できればプロに任せたいけど、どうやって依頼すればいいの?」
このようなお悩みを抱える方のため、HELP YOUでは経理業務のアウトソーシングサービスを行っています。
HELP YOUに経理業務をアウトソーシングすると
◎領収書のデータ入力や請求書発行など、あらゆる経理業務が片付く
◎現状の課題から最適なフローを導き出し、業務効率化も実現
◎経理業務の負担が減ることで、コア業務に集中できる環境が整う
HELP YOUは一緒に課題を解決するパートナーとして伴走し、貴社の業務効率化を実現します。クライアント様への導入実績は900以上。
この機会にアウトソーシングを導入し、自社の価値創出に注力しませんか?
ご興味のある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)