【DXの進め方】中小企業DX推進の具体的なステップ
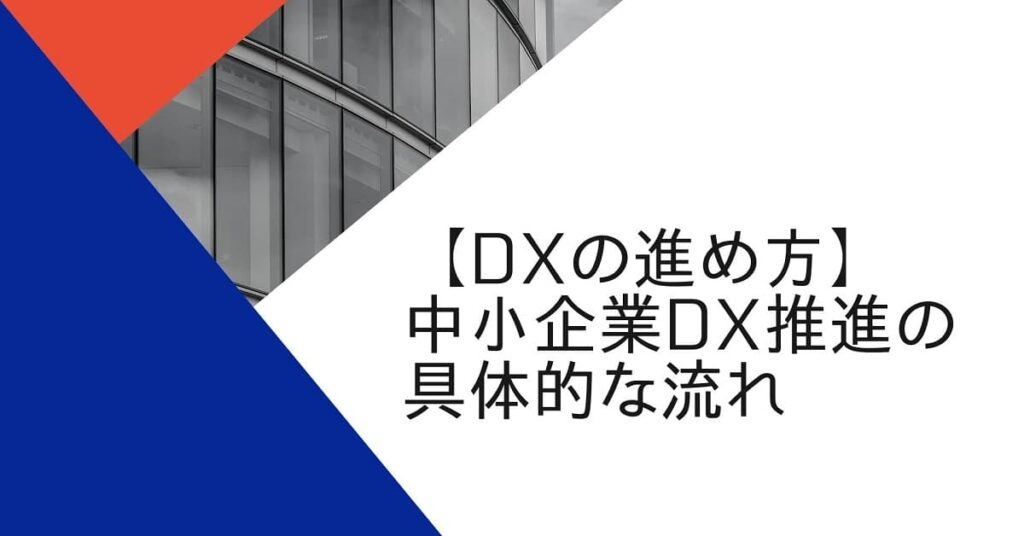
企業経営においてDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性は理解しているが、自社の企業規模で必要なのか、何を行ったらよいのか進め方が分からないという企業経営者・推進担当者の方もいるでしょう。
この記事では、中小企業におけるDXの進め方・推進をサポートするサービスをご紹介します。
この記事を読むことでDXの必要性を理解し、自社の変革に向けてDX化を推し進めていくことが可能になります。
DXの進め方を知る理由
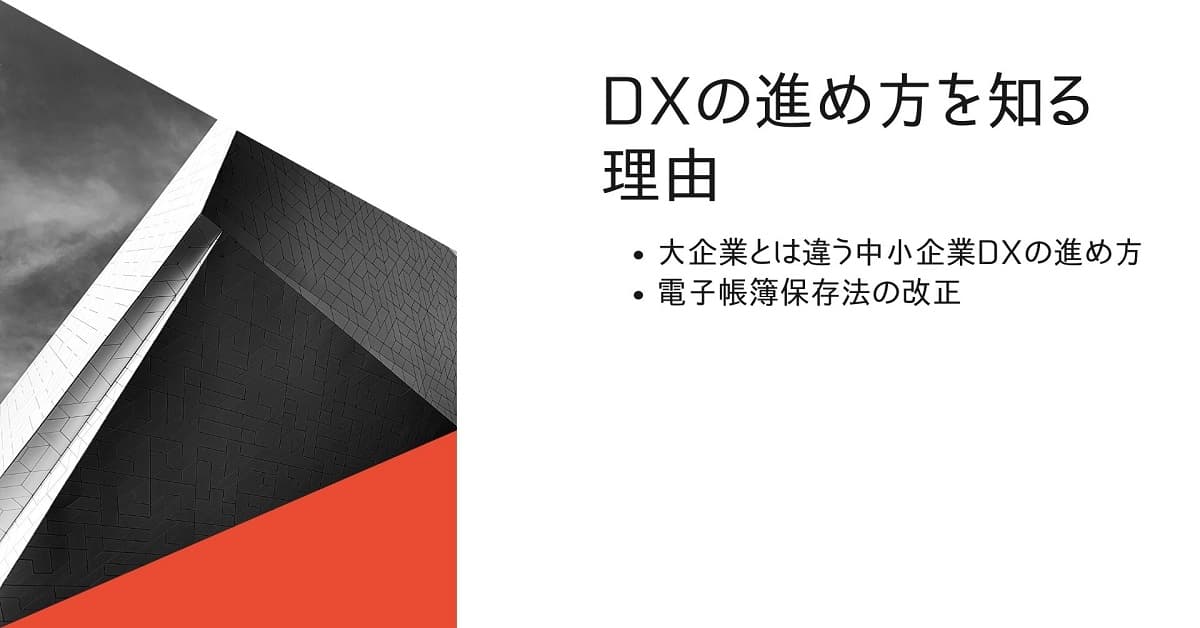
DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略語であり、デジタル技術を用いて企業の業務やビジネスモデルを変化する取り組みです。DXを推進するための目標やゴールは各企業ごとに違い、そこに至る進め方も様々です。そのためDX化の過程で方向性を見失うことがないよう、あらかじめ自社に適した進め方を知っておく必要があります。
大企業とは違う中小企業DX進め方
DX推進の情報が溢れているものの、進め方に関する事例が大企業のものばかり取り上げられているのが実情です。
そうした事例は中小企業の現状には即しておらず、参考にして取り組める内容が少ないと感じる経営者・推進担当も多数いるでしょう。
企業それぞれに最適の戦略があり進め方も千差万別です。
大企業と同様の推進コスト・人材がそろっていなくても自社に合った進め方を見つけ、それを実行していくことが重要です。
電子帳簿保存法の改正
企業のDX推進の第一歩は情報のデータ化です。データ化はDX推進には欠かせないビジネスプロセスのひとつです。
2022年1月1日に施行された「改正電子帳簿保存法」は、企業が情報のデータ化に着手する転機になります。
これまで紙ベースでの書類保管で問題なかったものが、猶予期間終了後の2024年1月1日以降、企業の全取引書類の、電子データでの保存が義務付けられます。
具体的な保存区分は以下の3つに分かれます。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引データ保存
紙の書類をスキャンして画像データで保存(上記2)・メールなどによる取引履歴のデータ保存(上記3)の2つはヒトと時間を費やせば可能ですが、人繰りなどの理由で手間と感じる企業もあるでしょう。
担当者の手間を考慮した場合、作成した帳簿・決算書類などを電子データのまま保存(上記1)する方法が現実的です。
これは会計管理システムなどを導入することで、作成した書類をデータのまま保存することを意味します。つまり情報のデータ化を推し進めることです。
電子帳簿保存法の改正の猶予期限が迫ってきていることもあり、情報のデータ化を推進するきっかけにするとよいでしょう。
参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました(2021年5月)」
参考:経済産業省 ミラサポplus 「どうすればいいの?『電子帳簿保存法』」
DX推進に必要な取り組み

DX化を進めるためには中長期的視野に立ち、スピード感を持って実行することが重要です。DX推進における必要な取り組みを解説します。
業務プロセスの効率化
DX推進でもっとも重要な取り組みのひとつが、業務プロセスの効率化です。
新しいシステムの導入や、複数の部署・担当が携わる業務の流れを自動化するなど、「業務プロセスのデジタル化」(デジタライゼーション/Degitalization)によって業務を効率化し、生産性の向上につなげます。
例えば、取引先に請求書を発行する場合以下の流れになります。
【業務プロセスがアナログの場合】
- 営業担当が紙ベースの請求書発行依頼書を作成・経理に依頼
- 経理担当が依頼書を目視チェック
- 経理担当が経理システムに登録し請求書を作成・発行・送付
【業務プロセスをデジタル化した場合】
- 営業担当がデータベースに取引先の月次の請求書発行日を登録
- システムが取引先の請求書発行日を自動抽出。自動で請求書作成・発行
システム化により人為的ミスの削減もつながり、企業としてのサービスの向上も実現する業務プロセスのデジタル化は、企業のDX推進におけるポイントなのです。
業務のデジタル化
デジタイゼーション(Degitization)とも呼ばれる業務のデジタル化は、DX推進における最初に取り組む作業です。
今まで紙などのアナログツールで行っていた作業・管理を全てデジタル化します。
具体的には押印による承認作業を停止し、オンライン上で承認作業を行うことや、ペーパーレス化などがこれにあたります。
DXは業務・業務プロセスの全てをデジタル化し新たなビジネスモデルの創出・業務の変革が目的となるため、業務自体の脱アナログ化は必須です。
社内の連携
DX推進には経営者から社員まで社内の連携が必須です。
経営者・経営陣がDX化の必要性・ビジョンを全社に共有・浸透させることで、同じ意識を持った社員がDXを推進します。
DXは会社自体が変革するもので、部署単位で別々に行うものではありません。
部署ごとに別々の管理システムがある場合は、システム連携やシステム統合、全社一元管理システムの開発も必要でしょう。
DX推進担当部署を中心に各部署の協力・連携しながら推進することでスピード感のあるDX化が見込めます。
DX人材の獲得
デジタル知識・スキルを持ちデジタル技術に精通しているのがDX人材で、企業のDX化の中核をなします。
DX人材を中心にDXを推進しますが、企業にそうした人材がいない場合は採用活動で獲得します。
ただ専門人材の枯渇が社会問題になっている昨今、その獲得は困難です。そうした場合は社内の適性のある人員をピックアップし、育成することも視野に入れるとよいでしょう。
DXの進め方|中小企業のDX具体的なステップ

企業のDX推進の基本的な取り組みについて紹介しましたが、実際に中小企業が他社に先んじてDX化を実現し優位性を確立するための具体的な手順を解説します。
DX推進の目標設定
企業がDX化に向けて最初にすべきことは、経営者・経営層によるDX推進の目標・目的・ビジョンの設定です。
- デジタル技術を活用して自社のビジネスにどのような変革をもたらしたいのか
- DX化によりどのような価値を創出するか
- なぜDXが必要なのか
自社のDX化の根幹となるビジョンを明確にすることで、現状の課題・具体的な施策の検討をスムーズに行えるようになります。
DXの目標がない企業は、管理システムの導入など業務のデジタル化がゴールになってしまいビジネスモデルの変革を実現できません。また、経営者・経営層がDXを理解せず、現場に丸投げすることも成功しない要因になり得ます。
そうしたことがないよう、まずは経営者自身がDXの必要性を理解し、自社のDX推進の目標を設定することが重要なのです。
参考:経済産業省 「DX推進指標(試行版)※定性指標」
ビジョンの共有
経営者・経営層が設定したDX推進の必要性・自社のビジョンを全社的に共有します。
社員による質問・反対意見が出た場合は、経営層が真摯にビジョンを伝え・理解の浸透を図りましょう。
全社員が共通理解の上でDX推進を行うことで、会社の方向性に対する認識やフェーズのズレがない、スピード感を持ったDX化が可能になります。
同時にDX化のエンジンとなるDX推進チームを発足。部署横断型で編成したDX推進チームを中心に組織整備・人材や予算配分・仕組みの構築・システム導入検討などを行います。
経営者・経営陣が策定したビジョンをベースに、自社に最適なDXによる変革を実現するのです。
課題の明確化
DX化を推進するために自社の現状と課題を把握します。
- アナログ作業はないか(例:紙による勤怠管理)
- 部署ごとに独自のシステムを導入していないか
- 老朽化したシステムを使い続け作業効率が落ちていないか
- システムに後付けした機能があるためブラックボックス化していないか
上記は一部の例ですが、今まで当然のように行っていた全ての業務を可視化し、業務効率化・生産性向上を阻害している要因を抽出します。
ビジョン実現に向けた自社の現状・抱えている課題を洗い出すことで、DX化に向けた実際のアクションにつなげていきましょう。
リソースの確保
まずは、リーダーシップを確立します。上層部がDXの重要性を理解し、その変革をリードする意欲とビジョンを持つことが重要です。トップダウンの支援や投資が必要だからです。
必要な技術、
その上で、専門技術持った人材を確保し、プロジェクトチームを立ち上げます。ツールの導入や予算などのリソースも確保します。
社員の意識共有
DX化へのビジョンを全社的に共有し新規システムの導入を進めていても、新しいビジネスモデルの創出を目指す社員の意識が共有できていないと新しいシステムを使いきれない可能性があります。
DX推進チームだけに変革を任せきりになってしまったり、他部署が疎外感を感じてしまったりすることがないよう、経営者・経営陣が陣頭指揮をとりDXを推し進めていきましょう。
DX化は中長期的なプロジェクトですが、定期進捗報告・DX推進による成果共有など、全社員が常に当事者意識を持てるような働きがけを行います。
業績・人員体制などにより状況は常に変化します。その時点の状況に合わせて自社に最適な方法でDXを推進しましょう。
一方DX化の過程で、残業の増大など社員に負担を強いる可能性があります。社内ルールの整備・バックアップ体制の構築なども忘れずに実施することをおすすめします。
ワークフローのデータ化
アナログ業務のデジタル化・DXに対する社員の意識が共有できたら、会社全体のワークフローのデジタル化に着手します。
【ワークフローのデータ化の例】
- システム上で稟議申請・承認・回付を行うワークフローシステムの導入
- 勤怠管理・給与管理データを連携させ給与明細を自動作成
- 顧客データと経理システムを連携し月次の自動決済に活用
- 全部署が活用できる新しい基幹システムの構築
社内各部署で管理されているデータ同士の連携や、全社で一元管理できる新システムの導入など、各業務をデジタルでつなぐことで、生産効率の向上・コスト削減・売上向上が見込めます。
新たなシステムの構築・顧客情報の管理・システムによる経理処理など、ワークフローの全てデータ化し管理するのは困難な場合は、外部のアウトソーシングサービスの活用・各自治体に相談するとよいでしょう。
収集データでビジネスモデルを変革
アナログからデジタル化し、社内に蓄積・収集したデータは企業変革のヒントとなります。
デジタル技術によるビジネスモデルの変革に努めても市場動向・情勢の変化など内外の要因により微調整が必要な場合もあるでしょう。
そうした要因に対応するためにも、収集データを分析・活用し定期的な見直しを行います。
その結果、PDCAサイクルを回すことで自社のビジネスモデルに変革をもたらす可能性が生まれます。
経済産業省発表のDX推進指標で、DXにおける見直すべき事項と自社の状況(成熟度)がチェックできます。
常に自社に最適なビジネスモデルの変革は何か・自社DX化の進捗に目を向け、状況把握・検証・実行を繰り返すことで変革を推し進めていくことが重要なのです。
参考:経済産業省 「DX推進指標(試行版)※定性指標」
中小企業のDX人材

大企業においてもDX人材の確保が難しい昨今、中小企業におけるDX人材の確保はさらに困難といわざるを得ません。それでは中小企業はどのようにDX人材を獲得するにはどうしたらよいのでしょうか。
中小企業のDX人材獲得は厳しい
企業のDX推進において人材の確保は重要課題のひとつです。
経済産業省によると2025年には人材が枯渇し、127万社の中小企業が廃業する可能性があると予想されています。また同年には505万人の労働人口不足が発生。中でもDX化の中核をなすIT人材が約43万人不足するといわれています。
企業規模に問わずDX人材が枯渇するため人材不足への対応が急務となっています。
DX人材を確保し、DX化による業務効率化・生産性の向上に努めないと企業の存続すら危ぶまれることを意味します。
大企業でも課題となっているDX人材の確保は中小企業ではさらに困難となるでしょう。
採用・育成を通じていかにDX人材を確保するのか、経営者・経営陣が早期に検討しておくべき課題なのです。
出典:中小企業庁 「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」
出典:パーソル総合研究所 「労働市場の未来推計2030」(2018年2月21日公開)
参考:経済産業省 「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」(平成30年9月7日発表)
DX人材は社内から
新たな人材の採用が困難な場合、社内の人員の中からDX人材を育成する必要があります。
一般的に以下のような人材がDX職の素質を持った人材といわれています。
【DX職の素質も持つ人材】
- 業務に精通している
- PC操作に抵抗がない
- 自社をよくしたいという強い思いがある
ピックアップした人材にデジタル知識・スキルを習得してもらうことで、DX人材として育成します。
中小企業の場合、必要となるデジタル知識はプログラミングではなく、ノーコードで十分です。ノーコードを使用すれば自社でプログラミングが必要なシステム・アプリの開発も可能になります。
経営陣はDX人材が必要となる権限を委譲し、各人材が動きやすいように役割を明確にするとよいでしょう。
データ化のご相談は「HELP YOU」へ

社内のリソースのみでのDX化は心配という企業も多数あります。
DX推進はスピード感を持って行う必要があることは理解するものの、肝心のアナログ作業のデータ化に行き詰っている企業もあるでしょう。
そうした企業はアウトソーシングサービスを活用することをおすすめします。「HELP YOU」は企業のDX化のバックアップを行います。
HELP YOUとは
HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。
【HELP YOUのプラン】
<チームプラン>
お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。
2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能
3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」
4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能
チームプランの主なサービス内容
HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。
■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など
■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など
■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など
■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など
■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など
■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など
※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。
チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。
「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください!
DXの進め方まとめ
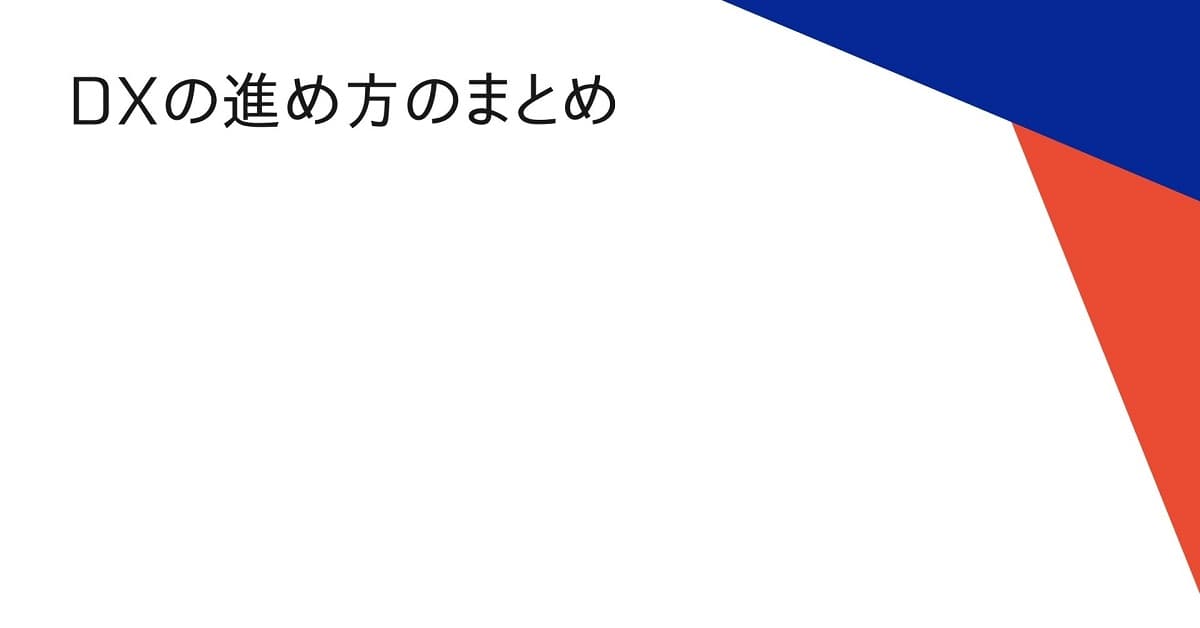
DX推進が企業規模に問わず急務となっている昨今、中小企業においてその波に乗り遅れることは、企業存続が危ぶまれる可能性があることを意味します。
自社に適したDXの進め方を理解し、中小企業の経営者・経営陣が先頭に立ちDX化を推し進めなければなりません。
スピード感を持って着実にDX化のプロセスを歩むことで、自社ビジネスモデル・マーケットに変革をもたらすDXが実現するでしょう。
▼合わせて読みたい
オンラインアウトソーシングはHELP YOU
1,000以上のクライアント様が導入
人手不足が深刻な状況で、業務を外注する企業が増えています。
特にオンライン上のアウトソーシングサービスは、下記の点で多くのお客様に選ばれています。
【HELP YOUが選ばれる理由】
1.厳しい採用プロセスをクリアした「優秀なアシスタント」が業務を担当
2.チーム制だから人材が退職して業務が滞るリスクなし!長期的な依頼が可能
3.専属ディレクターがつくため、様々な業務をまとめて依頼できる
日々の雑多な作業を外注し、重要な業務に集中して生産性を上げたい方は
ぜひこの機会にHELP YOUの導入をご検討ください。
お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)
